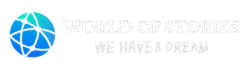「キャリア」や「社会課題」という言葉は、大切なのは理解している。でも、それを自分のこととして実感するのは、まだ少しむずかしい――。そんな学生たちに、自分の“未来”について考えるきっかけを届ける特別授業が、岡山大学で開講されました。
授業名は『地球社会の課題解決を仕事に ― 世界の次世代リーダーから学ぶキャリア ―』。
世界最大級の次世代リーダーサミット「One Young World(OYW)」の公式パートナーである岡山大学の副学長・横井篤文教授の協力のもと、実現した授業です。
対象は、大学1年生約100人。 “キャリア”や“社会課題”についてまだ漠然としたイメージしか持てていない学生たちが、自分の内面と向き合い、未来に一歩踏み出すための全7回の授業になりました。
本記事では、この授業でどのような学びがあったのかに加え、参加者として招かれた「ドリーマー」の声、そして授業を通じて言語化された「学生たちの夢」をご紹介します。
※画像は昨年度の授業の様子
世界と出会う特別な授業、その中身とは?
この授業の最大の特徴は、単に知識を得るだけの場ではなく、「自分の夢を言語化するプロセス」に重きが置かれていたこと。 教科書として使用されたのは、世界201カ国の若者たちの夢を集めた書籍『WE HAVE A DREAM』です。
授業では、ネパール・インド・オマーン・ルーマニア・フィリピンの5ヵ国から、実際に社会課題に取り組む若きリーダーである“ドリーマー”たちがオンラインで登壇しました。
彼らの人生のリアルなストーリーに触れながら、「グローバルに働くとは何か」といったテーマについて、深く考える時間になりました。また、学生たちの投票によって登壇が決まったドリーマー(フィリピンのアリーザさん)のように、学生の関心から授業内容が形づくられていくという特別な試みも一つの特徴です。
学生たちは、講演を聞くだけでなく、自分自身の夢についてじっくりと考え、書き出し、毎回シャッフルされたクラスメイトと対話を重ねていきました。そして、「今の自分」や「これからどう生きていきたいか」といった未来の理想像に加え、「なぜそう思うのか」という原点にも立ち返りながら、少しずつ自分の夢を言葉にしていきました。
授業の終わりには、それぞれが辿ってきた背景や価値観が映し出された、「自分だけのドリームストーリー」が形になっていったのです。
ドリーマーからのメッセージ:夢は距離を越える
授業のハイライトは、なんといっても世界5カ国で社会変革に挑むドリーマーたちとのオンラインセッション。彼らは授業後、日本の学生との交流をどのように感じたのでしょうか?心温まるメッセージをご紹介します。
アナミカさん(インド)| 国連職員、スイス勤務 ※当時
この授業が「何をするか」だけでなく「なぜそれをするのか」を問う、特別な場であることに深く感銘を受けました。特に、ある学生の「今日まで、SDGsはとても遠い存在に感じていました」という言葉には、心を打たれました。これこそ、私が届けたかったインパクトです。この経験は、「本当の変化は、政策室や大きな組織ではなく、若者たちが深く考えるこのような教室から始まるのだ」という私の信念を、さらに強いものにしてくれました。
ガブリエルさん(ルーマニア)| 社会課題を起点としたプロダクト開発するエンジニア
情熱あふれる100名以上の学生が、世界で「目的意識を持ってリードする」とは何かを探求する姿は、本当に素晴らしいものでした。学生からは「グローバルな課題に興味が湧いた」「世界観が広がった」といった、嬉しいフィードバックがたくさん届きました。私が目の当たりにしたのは、世界に挑戦する準備ができた、可能性に満ちたチェンジメーカーたちの姿です。皆さん、これからも大胆に夢を見て、勇敢に行動し続けてください!
アリーザさん(フィリピン)| イスラムとキリスト教徒の両親を持つ平和活動家 マーケティング会社を運営するデュアルキャリア実践者
私の話の中心は、夢を追う中での「個人的な挑戦」でした。驚いたのは、多くの学生が「共感できる」と感じてくれたことです。私たちは、言葉や文化が違っても、同じようにプレッシャーに悩み、間違いを恐れる人間なのだと改めて感じました。辛い時期に「独りじゃない」と感じられる繋がりこそが大切です。この経験を分かち合ってくれたクラスの皆さんに、心から感謝します。皆さんの方が、私をたくさん助けてくれました。ありがとうございます!
ドリーマーたちから声は、国境を越えて、岡山大学の学生たちの心に確かに届きました。
岡山大学の学生たちが描く、新たな未来図
5人のドリーマーたちとの出会いは、学生たちにどんな影響を与えたのでしょうか。
授業を通して形成されたドリームストーリーには、それぞれの人生に根ざした「夢」が綴られていました。その一部を紹介します!
Aさんの夢:「世界中の子供たちが飢餓で、苦しまないように気候変動に強い作物を開発したい」
私の夢は、気候変動に強い作物をつくり、世界の飢餓問題を解決することです。
発展途上国では、気候変動の影響でたくさんの人々が満足にごはんを食べられずにいます。私は研究者として、英語も使いながら、この問題を解決できる作物を開発したい。そのために今、農学と英語の勉強に励んでいます。
お米一粒も残さない、といった日々の小さな意識が地球を変えると信じています。私は今も、皆さんのように上手に話すことはできません。でも、自分にできるやり方で、必ずこの夢を叶えたいです。
Bさんの夢:「英語で会話ができるようになって様々な国を回り、文化、歴史を知りたい!」
私の夢は世界中に行って文化や歴史を知り世界の知識が豊富な人になることです。
その一番の原点は、高校生の時に京都で出会ったネパール人観光客との交流でした。つたない英語でも、一生懸命伝えようとすることで心が通じ合った瞬間、「自分の世界が広がる」という感覚を実感し、よりたくさんの人と交流したいと思うようになりました。また今回の授業で、争いの多くは相互理解の欠如から生まれると学びました。だからこそ、他国の価値観や文化を自分の目で見て知ることが、とても重要なことだと感じています。
Cさんの夢:「食物アレルギーの特効薬をつくりたい!」
私は、食物アレルギーの特効薬を開発し、幸せを感じてもらうことが夢です。
私自身、最近まで生まれつきのアレルギーがありました。給食の時間には「なぜ自分だけ食べられないんだろう」と悔しい思いをしたこともあります。
高校三年生でアレルギーが治り、今まで食べられなかったものを初めて口にした時の「こんな味だったのか!」という驚きと喜びは、今も忘れられません。
この喜びを、今もアレルギーで苦しむ友人や世界中の人々に届けたい。食の新しい世界を見てほしい。その一心で、岡山大学で化学を学び、将来、多くの人を幸せにできる薬を開発したいです。
世界中のドリーマーと夢を語り合う経験は、学生たちにとって、自分の未来を描くヒントになったようです。
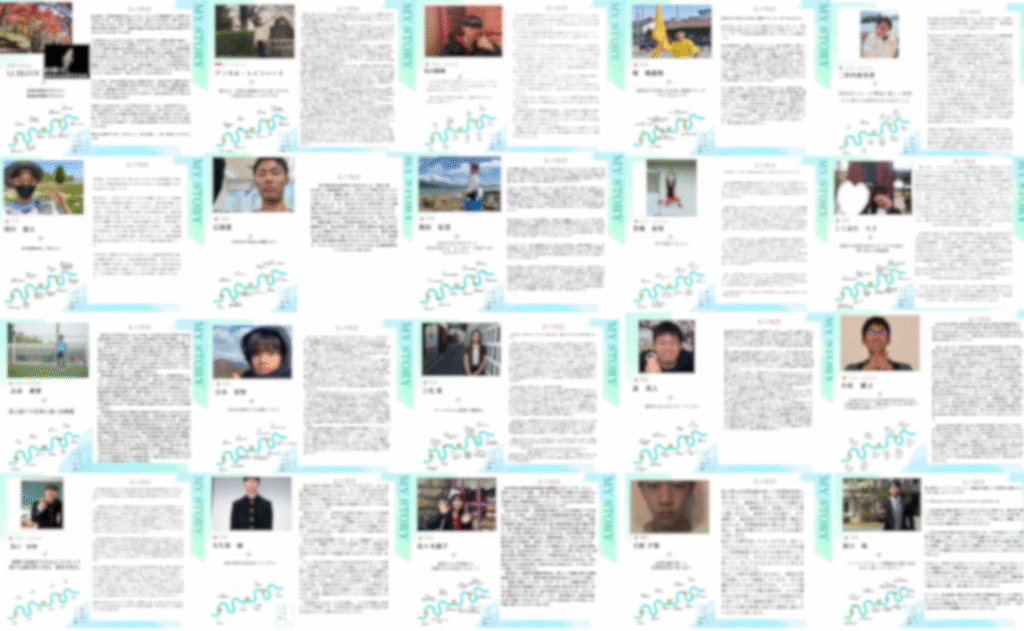
↑学生たちが自身の夢を言語化した最終アウトプット
小さな経験が夢のヒントに
岡山大学で行われた全7回の授業は、世界中のリアルな夢に触れながら、自分自身の「好き」や「これまでの経験」と向き合うことで、大切な価値観に気づき、それをキャリアへとつなげる――その第一歩を後押しする授業でした。
この記事を読んでいるあなたも、もしかしたら心の中に小さな問いが芽生えているかもしれません。「私にとってキャリアって何だろう?」と。そう思ったときは、まずは小さなことから始めてみてください。仲間との対話や、過去を振り返る時間の中に、キャリアのヒントは必ず隠れています。
そして、ドリーマーと岡山大学の学生の交流のように、世界中の人々と出会い、夢を語り合うことが、自分のヒントを見つける大きなきっかけになるかもしれません。
あなたの夢が輝き出す瞬間を、世界はきっと待っています。